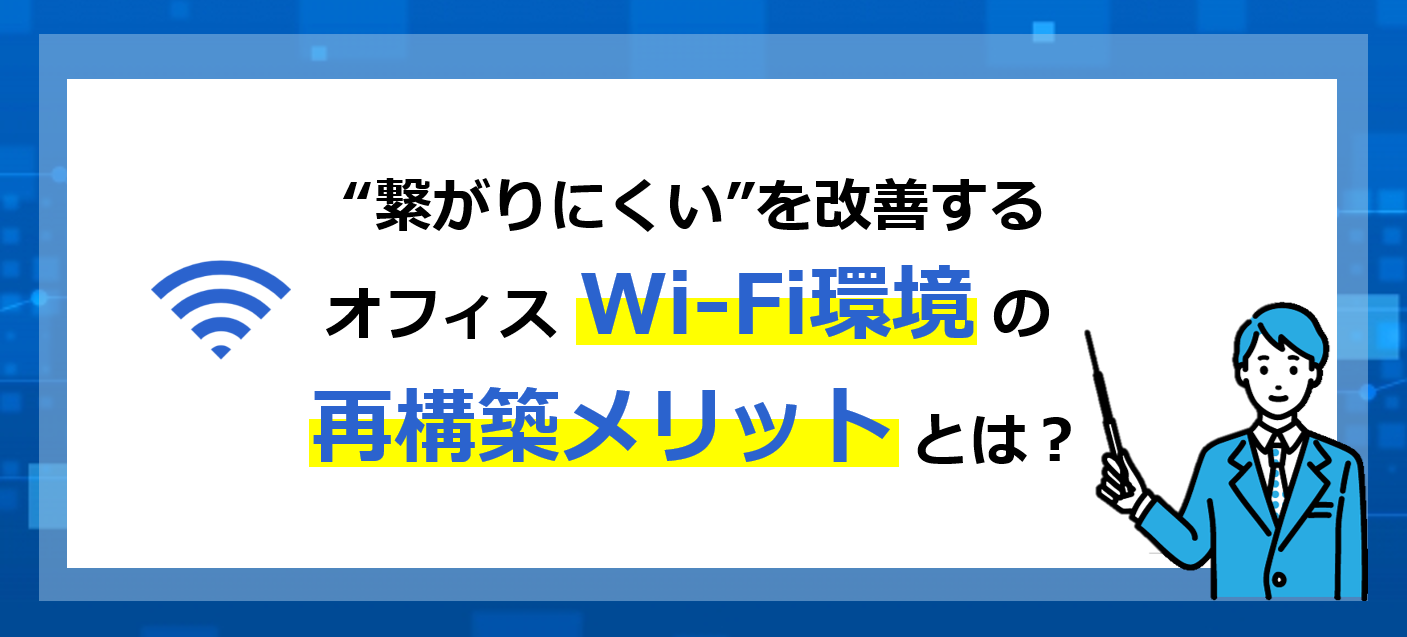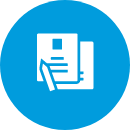EOLとは?リスクと企業が行うべき準備や対策をまとめて解説

技術の進歩とともに製品の寿命を迎えるEOL(End of Life)は、ビジネスの持続可能性やセキュリティの観点から無視できない要素です。EOLは、ソフトウェアやハードウェアといった製品がメーカーのサポートを受けられなくなる時期を意味し、これによりセキュリティ脅威や技術的な問題が生じるリスクがあります。この記事では、EOLの概要と重要性、EOL製品を使用し続ける際のリスク、そして企業が取るべき準備や対策について解説します。
EOLの基本概要と意味
EOL、すなわち「End of Life」は、ソフトウェアやハードウェアなどの製品がサポート期間を終え、その生涯を閉じる段階を示します。企業にとって、利用している製品がEOLを迎えることは避けられない現実であり、それに伴いセキュリティリスクの高まりや、操作性・互換性の問題など様々な問題が生じる可能性があります。未然にリスクを回避し、ビジネスの継続性を保つためには、EOLに関する知識と準備が不可欠です。
「End of Life」の全体像とその意義
先にもお伝えした通り「End of Life」(EOL)は、製品がそのサポート寿命を迎え、製造元による新たな更新やサポートの提供が終了する時点を指します。この段階になると、技術的サポートやセキュリティの更新が停止され、製品の正常な運用やセキュリティ対策が困難になります。結果として、使用している企業やユーザーに新しいリスクや課題をもたらすことになります。
たとえば過去にも、Windows XPやWindows 7のように、広く使用されていたオペレーティングシステムがEOLを迎えた際には、多くの企業や個人がシステムの更新や別のシステムへの移行の対応に追われました。とはいえEOLは製品ライフサイクルの自然な終点であり、技術の進歩や新しいニーズへの対応を促進する重要な役割を果たしています。
EOS/EOE/EOSLとの違い
EOLのほかにもEOSやEOE、EOSLといった似た用語があります。これらは製品サポートの異なる段階を表す用語で、それぞれ意味に違いがあります。
・EOS(End of Sales):メーカーが製品の販売を終了する時点を指す。
・EOE(End of Engineering):製品の機能に対する不具合の修正や新たなアップデートが終了する段階を指す。
・EOSL(End of Service Life):メーカーが販売した製品のアフターサービスや保守期間を終えることを指す。
これらの違いを理解することが企業にとって非常に重要です。なぜなら、製品ライフサイクルの各段階で、企業は対策を講じ、リスクを回避するために計画的なアップグレードや移行戦略を立てる必要があるからです。
例えば、EOSが近づいた場合、今使っているものと全く同じ製品は手に入らなくなることから、後継機の情報収集を始める必要があります。EOEはセキュリティの脅威に備える必要があるため、他の製品への移行を検討するタイミングといえます。そして、EOSLでは、メーカーの製品サポートがもはや受けられないことから、早急に入替えを行うか、サポートが可能なベンダーを探す必要があります。
これらのサポート終了関連用語を理解し、適切に計画を立て備えることで、企業はトラブルやダウンタイムを回避し、ビジネスの継続性を保つことができるのです。
EOL製品を使い続けるリスクと影響
EOL(End of Life)製品を使用し続けるという選択は、一見コストを削減できるかのように思えますが、セキュリティの脆弱性や互換性の問題、サポートが受けられないといったリスクを孕んでいます。これらの問題はデータ保護やシステムの安定性を損なう恐れがあります。企業にとって重要なデータが消失してしまったり、業務に欠かせないシステムが停止してしまった場合、実被害はもちろんのこと社会的信頼の失墜や企業のイメージダウンなど影響は広範囲に及びます。
EOLをむかえた機器はどうなるのか
EOLを迎えた機器は、メーカーによる公式サポートが終了することを意味します。これは、メーカーが新製品の開発に注力し、旧製品へのサポートを終了させるためです。例えば、Windows 7は2020年1月にサポートが終了し、それ以降はセキュリティ更新プログラムの提供が停止されました。こういった公式サポートの終了は、機器に重大なセキュリティリスクをもたらす可能性があります。既存の脆弱性が放置されるだけでなく、新たな脆弱性やセキュリティ上の問題が発見されても、修正や更新が行われなくなります。
よって、攻撃者による標的とされやすくなり、情報漏洩やシステム障害などのリスクが増大します。このように、EOLを迎えた機器を使用し続けることは、企業にとって大きなセキュリティ上の懸念をもたらすため、適切な対応策を講じることが重要なのです。
EOLが発表されたら何をすべきか
EOL(End of Life)やEOSの日程はメーカーがあらかじめホームページなどで告知しています。EOLの告知を受けたら、早急に次なる行動を検討する必要があります。EOLの対象製品の保有状況や影響範囲の確認、後継製品への移行計画の策定、ほかにもリスクを軽減するための措置などやるべき事を洗い出しましょう。すみやかに準備を進めることで、セキュリティの問題や互換性の問題を未然に防ぐことが可能になります。
EOLに向けて企業が行うべき準備
製品やサービスがEOLを迎えるにあたり正しい準備を行うことで、EOLのリスクを効果的に対処し、ビジネスの継続性を確保できます。企業の情シス部門は、常日頃からテクノロジーの進歩を見越した戦略の立案から、アップグレードやアプリケーションの移行計画の策定、必要に応じてメーカー以外の第三者機関が保守を提供する延長保守(第三者保守)サービスの利用検討など、複数の重要なステップを踏むことが求められます。
こういった準備により、EOLがもたらす可能性のあるリスクを最小限に抑えながら、持続可能なビジネスを維持することができます。
スムーズな移行のための戦略と計画
EOL製品から最新の代替品へのスムーズな移行を実現するためには、計画的に取り組む必要があります。EOLの発表を受けてから急いで移行を進めると、予期せぬコスト増加やシステムの稼働停止といったリスクに直面するおそれがあります。移行プランを事前に立て、システムを段階的にアップグレードすることで、移行にかかるコストを分散させ、業務に与える影響を最小限に抑えることができます。
移行プロジェクトを成功させるためには、その計画をしっかりと立て、実行に移すことが重要です。
アップグレードや移行のタイミングとリスクの軽減
End of Life(EOL)が近づくと、セキュリティや互換性の問題といったリスクが顕著になります。早期に移行計画を策定し、必要な検証・テストや準備を実施することで、移行プロセスが業務に与える影響を最小限に抑えることが可能となります。
アップグレードや移行計画の立案は、EOLの発表を受けた後、迅速に実施すべきです。計画的に進めることで、セキュリティの脆弱性によるリスクや予期せぬ業務途絶のリスクを避け、業務の継続性を保持することができます。早めに対策を講じることで、セキュリティの問題の発生を防ぎ、互換性の問題による業務の停滞を未然に防ぐことが可能です。
EOLをむかえた機器の継続利用
製品がEOL(End of Life)を迎えると、企業は新製品への移行を検討しますが、すぐにはできない場合もあります。このとき、継続利用という選択肢がありますが、メーカーのサポートを受けられなかったりセキュリティリスクや互換性問題などの課題が伴うので注意が必要です。これらの問題を最小限に抑え、機器のライフサイクルを延長するため正確な対策と準備が必須となります。
第三者保守という選択肢
メーカー以外の第三者機関がEOL製品のサポートを提供する延長保守サービスというものがあります。延長保守サービスはメーカーのサポートが終了した後も不具合の相談を行えたり故障時に修理をしてもらえたりと非常に有効です。例えば、利用している機器がEOLを迎え、メーカーからのサポートが終了してしまった状況でも、第三者保守ベンダーの延長保守サービスを利用することで、安心して製品の使用を続けることができます。
このように、EOL製品でも安心して使用を続けるためには、第三者保守を活用することが効果的な解決策となります。
第三者保守を活用するメリット
第三者保守ベンダーはEOLを迎えた製品で不具合が起こった際に、独自の保守体制や部品調達ルートによって不具合の原因特定や修理などの対応を行います。機器の利用期間を延ばすことで機器のライフサイクルも延長でき、投資コストの抑制が可能です。
さらに、第三者保守ベンダーのサービスを利用することで、カスタマイズされたサポートを受けられるというメリットもあります。独自のサポート体制を構築しているため顧客のニーズに柔軟に応じることが可能であり、企業の特定の要件や運用環境に合わせた保守プランを提供してもらえます。例えば、24時間365日体制のサポートや、特定の機器のみをカバーする特別な契約を結ぶことも可能で、これにより自社の運用に最適なサービスを受けることができます。
三和コンピュータの第三者保守サービス
三和コンピュータは第三者保守ベンダーとしてEOLをむかえた製品の延長保守サービスを提供しています。メーカーのサポート終了後も企業のITインフラの安定稼働を支える強力なサポート体制を整えています。
サーバーやストレージ等の機器がEOLを迎え、製造元からの直接的なサポートを受けられなくなった場合でも、三和コンピュータはメーカーに代わり技術的な支援や必要な部品の供給を継続し、システムの信頼性を保ちながら、ダウンタイムのリスクを最小限に抑えるサービスを提供します。これにより、企業はEOL製品を安心して使用し続けることが可能となり、予算や運用上の制約による急なシステム更新の必要性からも解放されます。
三和コンピュータの延長保守サービスの概要はこちらから。
サービス・契約形態や対応エリア、対応可能機種一覧などをご紹介しています。
まとめ
本記事では、EOL(End of Life)について、その基本概要、製品を使い続けるリスク、企業が取るべき準備や対策、さらには第三者保守の利用について詳しく解説しました。EOLに直面することは、多くの企業が避けられない状況ですが、適切な対応と準備を行うことで、その影響を最小限に抑え、ビジネスの連続性を確保することができます。EOL製品を現在使用している、またはその可能性がある企業は、今一度その対策プランを見直し、必要なアップグレードや移行計画を策定することが重要です。
また、第三者保守の利用を検討して、サポートが終了した製品のメンテナンス方法についても把握しておく必要があります。テクノロジーは日進月歩で進化し続けます。そのため、企業はEOLのリスク管理だけでなく、新しい技術へのアップデートや移行を常に考慮に入れることが求められます。将来を見据えた技術投資とリスク管理を継続することが、企業の持続可能な成長につながります。
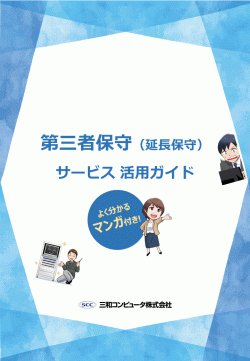
第三者保守(延長保守)サービス活用ガイド
第三者保守(延長保守)の概要と、三和コンピュータのサービス内容がわかる活用ガイド冊子です。
・マンガでわかる第三者保守(延長保守)サービス
・具体的な活用シーン
・契約形態やサービスレベルの種類
など掲載中。これ1冊で三和コンピュータの第三者保守(延長保守)がわかります!