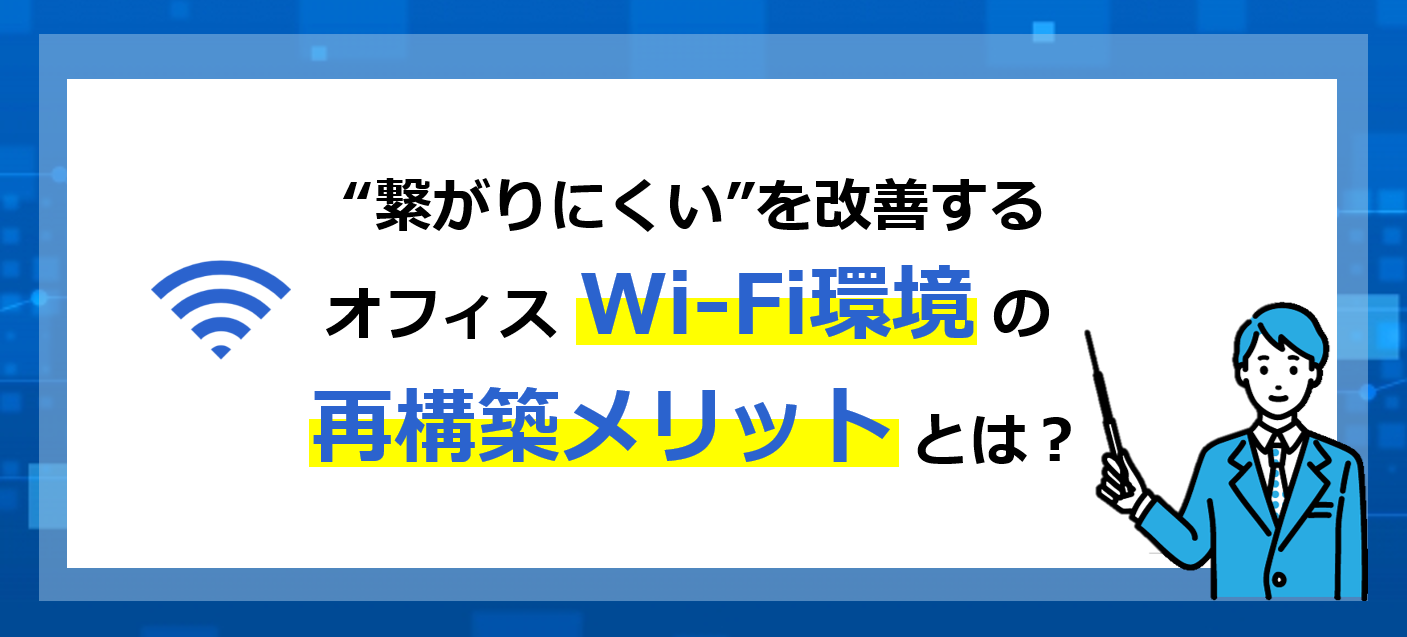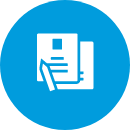頻繁に改正される法律に即対応できていますか?

労働基準法をはじめとした労務管理に関する法令は、改正が行われたり、新しい法律ができたりと、毎年のように対応が迫られます。法令遵守は企業活動を続けるうえで守らなければいけない大切な事項の一つです。
この記事では法令改正への対応にどのように準備していくべきかを紹介します。
目次
- 2023年4月1日に改正された法令内容
- 早急に対応が必要な時間外労働の割増賃金率
- 送金サービスの多様化による賃金(給与)のデジタル払い
- 2023年以前に改正された大きな内容
- 2024年以降に施行が決まっている内容、検討されている内容
- 法令改正に速やかに対応していくためには
- まとめ
2023年4月1日に改正された法令内容
労働基準法とは、1947年に制定された労働条件に関しての最低基準を定めた法律です。過去にもたびたび改正が行われていますが、2023年4月1日にもまた新たに改正労働基準法が施行されました。大きな変更対象となる内容は2つあり、「時間外労働の割増賃金率」「賃金(給与)のデジタル払い」となっています。
早急に対応が必要な時間外労働の割増賃金率
2023年4月1日に改正された労働基準法で影響範囲が大きい変更内容は「時間外労働の割増賃金率」の部分です。時間外労働とは1日8時間、週40時間を超える場合の労働時間を指します。2023年3月31日までは、中小企業での時間外労働における割増賃金率は25%でしたが、施行日以降は月に60時間を超えた分は50%へと引き上げられます。
送金サービスの多様化による賃金(給与)のデジタル払い
2023年4月の改正でもうひとつ大きく変わる内容は賃金(給与)のデジタルマネーでの支払いが可能になることです。賃金(給与)のデジタル払いとは、銀行口座ではなく、厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座に給与を振り込むことを指します。
労働基準法では、賃金の支払いは「通貨払い」が原則とされています(労働基準法24条1項)。しかし、通貨払いといっても現代では「現金の手渡し」で受け取っている人は少なく、多くの労働者は会社から銀行口座に給与の振り込みを受けていると思います。これは労基法では通貨払いを原則としつつも例外的に、労働者の同意を得た場合には、労働者が指定する銀行その他の金融機関の預貯金口座に振り込んで支払うことができるとされているからです(労働基準法施行規則7条の2第1項)。 これに対して、2023年4月1日の改正では労働基準法施行規則7条が改正され、賃金(給与)デジタル払いが可能になりました。
しかし、実際には「資金移動業者」が「指定資金移動業者」になるための厚生労働省への申請および審査についても法改正の施行と同じく2023年4月1日からの開始のため、運用開始にはまだ時間がかかることが想定されています。 とはいえ、キャッシュレス決済の浸透や送金サービスの多様化などにより、従業員から給与のデジタル払いの要望が挙がることも踏まえ企業側は準備をしていく必要があります。
2023年以前に改正された大きな内容
冒頭にも述べたように労働基準法は1947年に制定された法律であるため、時代の流れなどとともに度々改正が行われています。ここ20年の間では2003年、2008年に改正が行われたことに加えて、2018年には「働き方改革」関連法に伴う変更、2021年にはパートタイム・有期雇用労働法の改正が施行されました。
2003年の改正
- 専門業務型裁量労働制導入時の労使協定の決議事項の項目追加(健康・福祉確保措置等)
- 企画業務型裁量労働制の導入・運用の要件・手続きの緩和
2008年の改正
- 1か月に60時間を超える時間外労働についての割増賃金率の50%以上への引上げ(中小企業は当分の間適用を猶予)
- 上記の割増賃金の支払いに代えて代替休暇を与えることができる改正
2018年の働き方改革関連法に伴う変更
- 時間外労働の上限規制の導入
- 中小企業における月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の50%以上への引き上げ決定
- フレックスタイム制における精算期間の1か月から3か月への延長
- 特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設
- 有給休暇の年5日の取得義務の導入(対象者の条件あり)
2021年のパートタイム・有期雇用労働法の改正
同一企業内において、正社員とパートタイマー・有期雇用労働者の間の不合理な待遇差をなくして、どのような雇用形態であっても納得が得られる処遇が受けられ、多様な働き方を自由に選択できるように改正されました。大きく下記3つが変更されました。
- 不合理な待遇差を禁止
- 待遇に関する説明義務を強化
- 不合理な待遇差等に関する労使間のトラブル解決のため、行政による紛争解決援助制度の利用が可能
2024年以降に施行が決まっている内容、検討されている内容
このようにこれまでの間に世情の変化に伴い、労働基準法は改正が行われてきました。それでは、今回の2023年4月の改正のほかに今後どのような労務管理に関する法改正が検討されているのでしょうか。
2024年4月1日施行
①時間外労働の上限に関する猶予期間終了
2018年の働き方改革関連法に伴う2019年の改正労働基準法の施行以降、医師や建築業、運送業では時間外労働の上限規制の設置猶予が設けられていました。2024年4月からはほかの業種と同様に時間外労働のルールが適用されます。
②短時間勤務の障害者の実雇用率の算定基準
国、地方公共団体、民間企業は、障害者雇用促進法に基づき、その雇用する従業員について一定の割合(法定雇用率)に相当する数以上の障害者を雇用することが義務付けられています(民間企業の2023年現在の法定雇用率は2.3%)。
所定労働時間が一週間あたり、20時間以上30時間未満の短時間勤務の障害者については、障害者雇用率の算定において1人あたり0.5人としてカウントします。2023年4月時点では、所定労働時間が一週間あたり20時間未満の場合、障害者雇用率の算定においては雇用人数に含めることができません。
しかし、2024(令和6)年4月1日以降は、所定労働時間が一週間あたり10時間以上20時間未満の短時間勤務の障害者(ただし、精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者に限る)についても、実雇用率の算定において雇用人数に含めることが可能になり、1人あたり0.5人としてカウントします。
2024年10月1日施行
健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されます。社会保険の被保険者数が51人以上の会社を対象に、正社員の4分の3に満たない時間で働くパート・アルバイトなどについても、特定の要件を満たす場合には、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱い、社会保険に加入することが義務付けられます。
2025年4月1日施行
高年齢雇用継続給付の支給率が引き下げられます。60歳以上の従業員を再雇用する場合において、一定の要件(60歳時点の賃金額の75%未満)を満たした場合には、雇用保険から「高年齢雇用継続給付」が支給されます。現在65歳に到達するまでの期間、60歳以後毎月の賃金の15%が支給されますが、2025年4月1日以降は10%に引き下げられます。
法令改正に速やかに対応していくためには
このように、労務管理に関する法律は過去にも複数施行されたり、今後も改正が予定されていたりと時代によって変化してきています。働き方の変化や技術の改革などからその時々に応じて現行の法令規定に沿った給与管理や勤怠管理などを行わなければなりません。Excelによる手作業やタイムカードによる打刻、自社システムなど、どのような管理方法で運用していても、常に新しい法令基準に沿った管理方法に適用していく必要があることはどの企業も変わりません。
しかし、労務管理を手作業で行っていると、これらの対応に追われるばかりで日々のさまざまな業務が滞ってしまうことが想定されます。法令改正に速やかに対応するには、各種システムメーカーが提供しているパッケージシステムを使用したシステムを導入することが非常に有効です。
まとめ
労働基準法をはじめとした労務管理に関する法令は、改正が行われたり、新しい法律ができたりと、毎年のように対応が迫られます。法令を遵守することは企業活動を続けるうえで非常に大切な事項の一つです。新しい法令基準に沿った管理に都度対応するにはパッケージシステムを導入し管理することが非常に有効です。
三和コンピュータは会計や給与、人事・労務管理などの奉行シリーズを提供している株式会社オービックビジネスコンサルタント(OBC)の販売パートナーです。 当社は約3,000社ある販売パートナーの中でも、数少ない最上位パートナーに認定されております。カスタマイズ可能な奉行パッケージに対し、追加開発のライセンスを取得している認定者が複数在籍しており、中堅企業・大手企業・グループ企業までの業務改善提案から追加機能プログラムの開発、セットアップ、導入支援、ユーザーサポートまでをすべて自社で行うことが可能です。
法改正に伴う労務管理でお困りごとがありましたらお気軽にお問い合わせください。