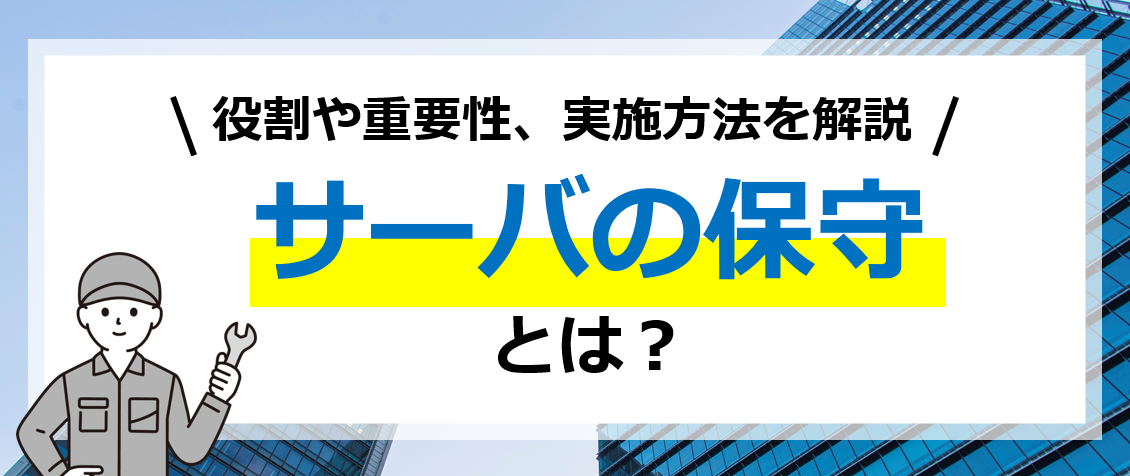
サーバの保守とは?役割や重要性、実施方法を解説
サーバの安定稼働とセキュリティを確保する上で、サーバ保守は欠かせない業務です。企業のITインフラを支える重要な存在であり、そのトラブル対応やメンテナンスを適切に行うことで、ビジネスの継続性や信頼性を高めることができます。
この記事では、サーバ保守の役割や重要性、具体的な実施方法、円滑に行うポイントについて解説します 。
目次[非表示]
- 1.サーバ保守とは
- 2.サーバ保守の重要性
- 2.1.システムの安定稼働への貢献
- 2.2.企業信頼性の維持
- 2.3.セキュリティリスクの軽減
- 3.サーバ保守の具体的な業務内容
- 3.1.障害や不具合の対応
- 3.2.定期的なメンテナンス
- 3.3.ハードウェアの点検と部品交換
- 4.サーバ保守を行う方法
- 4.1.専門エンジニアを社内で雇用する
- 4.2.メーカーに依頼する
- 4.3.第三者保守ベンダーに依頼する
- 5.第三者保守ベンダーと契約する際のポイント
- 5.1.年間契約とスポット対応
- 5.2.サービス内容と費用相場
- 6.三和コンピュータが提供する第三者保守サービス
- 7.第三者保守サービス活用ガイド
サーバ保守とは
サーバ保守とは、サーバ運用中の 障害やトラブルへの対応、定期メンテナンスなどサーバが安定して稼働するための作業を指します。
サーバ保守は企業のIT基盤を支える重要な取り組みであり、ハードウェアやソフトウェアの状態を常に最適に保つことでシステムの安定稼働を維持します。障害が発生した際には復旧対応を行い、運用停止時間を最小限に抑えることも求められます。また、セキュリティ脆弱性の修正やパフォーマンスの最適化を進める点もサーバ保守の大切な役割の一つです。こうした継続的なメンテナンスと対策によって、企業全体のサービス品質や信頼性を高めることが可能になります。
目的と役割
サーバ保守は、企業がビジネスを継続的に行うための屋台骨を支えています。サーバが止まることなく、安全かつ安定的に稼働し続けることが目的であり、障害が発生した場合には最小限の影響で素早く復旧することが求められます。
また、保守作業を通じて脆弱性を早期に発見し、セキュリティリスクの軽減やデータ保護の観点からも大きな役割を担っています。 特に基幹システムや各種サービスの継続性を支えるために状況把握を行い、必要なメンテナンスを実施していくことが重要です。
運用と保守の違い
運用は日々の監視や運営管理など、問題が起きないようにするための定常作業が中心です。一方、保守は障害対応やメンテナンスを含む、問題への直接的な対処にフォーカスするところが特徴といえます。
例えば、定期的なバックアップからシステム更新、緊急トラブル発生時の復旧作業まで、保守は問題解決のプロセスを構築し、状況に応じて適切な対処を行います。運用と保守両方を適切に実施することで、安定したサーバ稼働を実現し、企業の信頼性を高めることが期待できます。
サーバ保守の重要性
サーバ保守を怠ると、企業活動全体に影響を及ぼすリスクが高まります。ここでは、その重要性を3つの観点から見ていきましょう。
サーバが停止することは、日常業務の遅延や顧客へのサービス停止に直結し、企業の信頼性を大きく揺るがしかねません。万一のトラブル発生時でも早期復旧が可能な仕組みを整えておくことで、企業が受けるダメージを最小限に抑えることができます。また、定期的に行うメンテナンスや検証を通じて、未然に障害を防ぐことが重要です。
システムの安定稼働への貢献
サーバ保守を適切に行うことで、稼働時間を最大化し、システムダウンによる業務停止を防ぎやすくなります。
定期的なパフォーマンス監視やログ分析を行うことで、小さな兆候を見逃さずに対策を講じることができ、安定的なサービス提供につながります。これにより、企業全体の生産性向上や顧客満足度の確保にも貢献できるのです。
企業信頼性の維持
サーバが停止しシステムの障害が長引くと、取引先や顧客からの信頼を失ってしまう可能性があります。
サーバ保守では、迅速な復旧手順やバックアップ対策を確立しておくことが不可欠です。万が一のトラブル時に最低限の被害で抑えられれば、外部からの評判を守り抜くことにもつながり、企業の信用を高い水準で維持することができます。
セキュリティリスクの軽減
脆弱性へのパッチ適用や最新のセキュリティアップデートを行うことは、サイバー攻撃や情報漏えいを防ぐうえで極めて重要です。サーバ保守を通じて定期的にシステムをチェックし、不審なアクセスやログの異常を早期発見することで、大きなセキュリティインシデントを未然に防ぐことができます。
安定稼働のための技術的対策と並行して、セキュリティ強化への取り組みを続けることが、企業を守るうえで欠かせません。
サーバ保守の具体的な業務内容
実際にサーバ保守としてどのような作業が行われるのか、その代表的な業務を3つに分けて紹介します。
サーバ保守の現場では、障害や不具合への迅速な対応が最優先とされます。一方で、定期的なメンテナンスやハードウェアの点検は、サーバの寿命を延ばし、トラブルを予防するうえで欠かせない作業です。これらの活動は、企業が長期にわたって安定したITサービスを提供するための基盤づくりに直結しています。そのため、担当エンジニアや保守ベンダーが協力し合い、効率的に実施することが重要となります。
障害や不具合の対応
障害対応の最初のステップは、問題がハードウェア起因なのか、ソフトウェア起因なのかを迅速に切り分けることです。ログ解析や監視ツールの情報を基に、原因を特定した後は、代替機器の準備・交換や設定変更を行い、サービスの停止時間を最小限に抑えます。復旧後には再発防止策を検討し、継続的な改善を実施することが理想的です。
定期的なメンテナンス
定期メンテナンスでは、OSやアプリケーションのアップデートをスケジューリングして行い、既知の脆弱性を早めに防ぎます。バックアップの取得やソフトウェアのバージョン管理も合わせて行うことで、不測の事態が起きた際にシステムを素早く復旧できる体制が整います。また、ログを定期的に確認しアラートが出ていないか、パフォーマンスに問題がないかをチェックすることも重要なプロセスです。
ハードウェアの点検と部品交換
物理サーバの場合、内部パーツの劣化やホコリの蓄積による熱暴走など、定期的にチェックしなければならない要素が多数存在します。ハードディスクのS.M.A.R.T.情報 やファンの動作状態を把握し、必要に応じて部品交換を行うことで重篤な障害を未然に防げます。こうした細やかな点検とメンテナンスが、サーバ全体の長寿命化と安定稼働の実現につながります。
サーバ保守を行う方法
サーバ保守には、社内エンジニアの確保、メーカーへの依頼、第三者保守ベンダーの活用など複数の方法があります。
自社の規模感や専門スキル、予算などによって選べる選択肢はさまざまです。社内にノウハウを蓄積できる体制を重視するか、コスト面や迅速な修理対応を求めるかなど、企業ごとの優先度によって最適解は異なります。特に近年はクラウド環境や仮想化技術の普及も進んでおり、保守形態の幅が広がっています。自社内での運用体制と合わせて、最も効率的かつ安心感のある保守方法を選定することが重要です。
サーバ保守を行うための3つの方法を紹介します。
専門エンジニアを社内で雇用する
自社でエンジニアを採用し保守作業を内製化する方法は、企業のITスキルを底上げし、ノウハウを蓄積できるメリットがあります。
また、トラブルが起きた際に社内のメンバーが即時対応できるため、時間や情報共有のロスを減らせる点も魅力です。ただし、人件費や教育コストが高くなるうえ、急激な技術進歩に追随するための研修や学習投資が欠かせません。
メーカーに依頼する
サーバメーカーに保守サービスを依頼することで、特定の機種に対して深い知識を持つスタッフのサポートを期待できます。安心してサービスを利用しやすい反面、契約期間やサポート範囲が明確に定義されているのが一般的です。
また、メーカーによっては連絡から対応までにリードタイムが発生する点にも注意が必要です。
第三者保守ベンダーに依頼する
メーカー以外の第三者保守ベンダーを活用する方法は、コストを抑えつつ幅広いサーバ機種に対応できる柔軟性が魅力です。多様なメーカーの製品知識を持っている場合が多く、独自ルートによる部品調達や迅速なサポートが受けられます。社内リソースが限られている企業にとって、専門家のアドバイスや保守の提案を受けてITコストを最適化できる有力な選択肢です。
第三者保守ベンダーと契約する際のポイント
前章で触れた第三者保守ベンダーと契約を検討する際は自社が求めるサービス内容やサポートレベルを明確にすることが大切です。契約時に注意すべきポイントを押さえましょう。
たとえばサポートレベルは障害対応の受付時間帯や修理時間帯、修理部品の在庫状況など、契約内容によって変わります。また、企業が求める可用性とコストのバランスをどう取るかも重要です。
特に24時間体制のサポートが必要な場合は、その分料金が上がることが多いため、実際に自社で必要な条件を見極めることが契約時のポイントとなります。
年間契約とスポット対応
年間契約は、定額で一定期間の保守サービスを受けられる方式であり、予算計画が立てやすい反面、利用頻度が少ない場合にはコスト負担が重く感じられることもあります。
一方、スポット対応は必要な時にだけ保守を依頼するスタイルで、頻度が低い企業にとってはコストを削減しやすい手段です。ただし、緊急時の対応速度やエンジニアの確保状況は年間契約より確実性が下がるケースもあるため、自社の運用状況とリスク許容度を検討して選ぶ必要があります。
サービス内容と費用相場
保守契約には、障害対応の範囲や対応可能時間、オンサイトかセンドバック対応かなど、細かなサービス内容が定義されています。自社環境で稼働しているサーバの機種や台数、必要となる稼働時間を考慮し、予算と求めるサポートレベルが合致するかをしっかり確認しましょう。サーバの機種や契約期間、内容によって費用は変動するため、業者に保守対応可否を確認して見積を取り、費用対効果を比較検討することで、自社に最適なサービス内容と費用相場の把握が可能になります。
三和コンピュータが提供する第三者保守サービス
三和コンピュータは、メーカー保守に代わる選択肢として第三者保守サービスを提供しています。
既にメーカーの保守期間が終了したサーバの障害復旧修理や、次期システムが稼働するまでの間の現行サーバの保守を行って欲しい時など、三和コンピュータの第三者保守サービスは有効な選択肢となります。当社は50年以上にわたり保守事業に携わり培ってきたノウハウがあり、NECや富士通をはじめとした幅広いサーバ機種の保守対応が可能なエンジニアが多数在籍しております。
ご要望にマッチするさまざまなサービスメニューをご用意しておりますので、サーバ保守に不安があるようでしたらぜひお気軽にご相談ください。
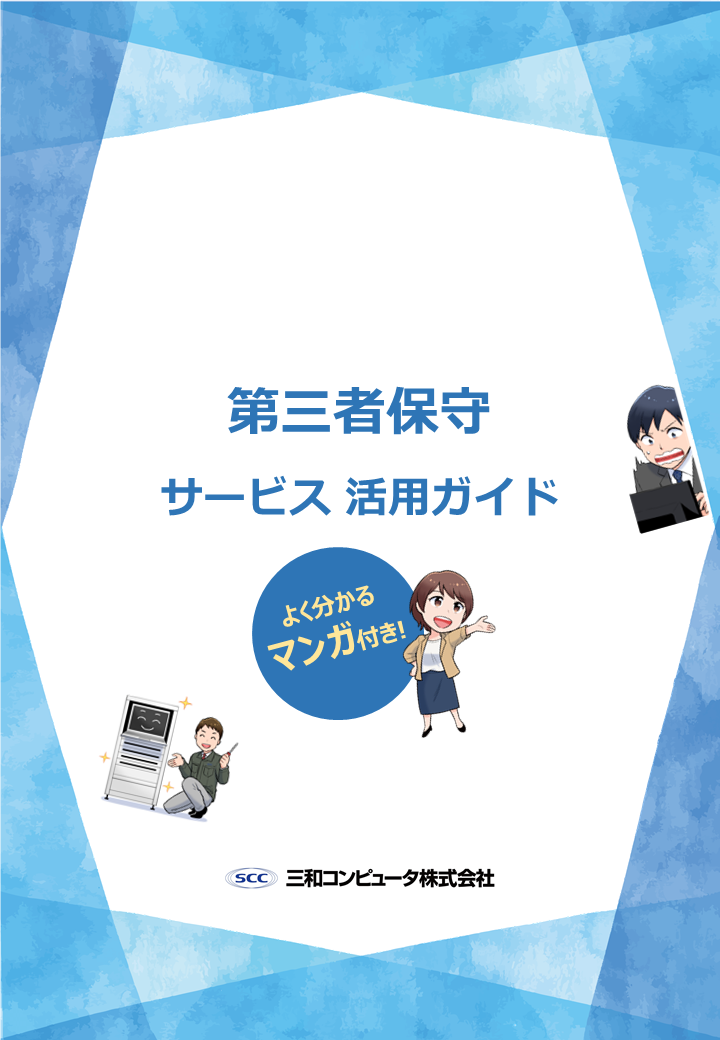
第三者保守サービス活用ガイド
第三者保守の概要と、三和コンピュータのサービス内容がわかる活用ガイド冊子です。
- マンガでわかる第三者保守サービス
- 具体的な活用シーン
- 契約形態やサービスレベルの種類
など掲載中。これ1冊で三和コンピュータの第三者保守がわかります!


